愛猫介護日記(その4)~発作への対策

痙攣発作対策の大変さ
2021年3月に痙攣発作を起こして倒れてから、目に見えて衰えが目立つようになった筆者の愛猫・ベンジャミン。
18歳という高齢ということもあり、それからは家族の誰かがなるべく側に付き添い、再度発作が起こった時には処方された発作止めの座薬をすぐに使用できるようにしました。

その後の半月足らずの間に、ベンジャミンは2回発作を起こしました。
どちらも家族が家にいる時間帯だったため、発作時に誰もいなくて頭を打って…などの最悪の事態は免れましたが、猫に座薬を入れることの大変さは、想像を絶するものでした。
猫用の座薬はそれほど大きなものではなく、しかも1回に付き1個の座薬を半分にしたものを使用するため、入れること自体は比較的すんなりできるのですが、すぐに外へ出てきてしまうのです。
その度に何度も入れ直し、困って獣医師に電話で相談して「なるべく奥の方にグッと入れる」などのコツを教えてもらったりもしましたが、猫が自力で排便できる間は、排便する時の要領で猫自身が外へ出してしまうのか、なかなかうまくいきませんでした。
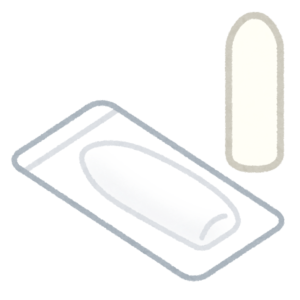
3回目の発作の時には、猫は発作がおさまった後に意識を失ってしまい、筆者も家族も
「死んでしまったのではないか!?」
と本気で焦りました。
その時は命には別状はなく、猫は数分後には実際、猫は数分後には意識を取り戻し、自力で歩いたり、フードを食べたりもしていました。
自力でトイレに行けなくなった日
しかし発作を起こす度に、ベンジャミンは少しずつ、でも確実に弱っていきました。
3回目の発作を起こした後の4月半ば頃からは、うまくトイレに行けなくなり、家の中で粗相をしてしまうことが増えました。
筆者が猫用の薬をもらいに動物病院へ出かけて帰ってくると、筆者の部屋の絨毯に粗相の跡があったこともあります。
ベンジャミンはとてもきれい好きで神経質で、トイレ以外の場所では絶対に排泄をしようとせず、尿検査の時になかなか尿が取れず困ったこともあったくらいでした。
そのベンジャミンが粗相をするということは、身体の状態がとても悪くなっているということ。
だから叱ることもできず、黙々と後始末をしました。

その後ベンジャミンは、トイレに行こうとしたものの自力でトイレの中に入ることができなくなり、トイレの目の前で粗相をしてしまうようになりました。
便も少しずつ「垂れ流し」のような状態となったため、家族がベンジャミンの行く場所に常にペットシーツを持ってついていく状態に。
そのうちに後ろ足が立たなくなり、前足で下半身を引きずって歩くようになったため、4月15日から猫用の紙オムツを履かせることになりました。
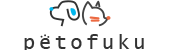











この記事へのコメントはありません。